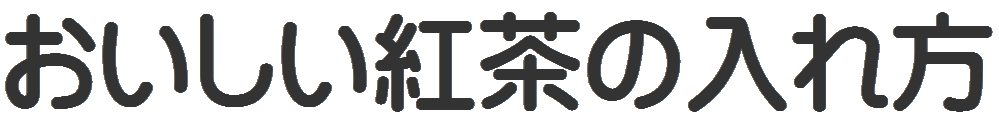紅茶の歴史は中国から
紅茶は中国南西部の「雲南」、チベット、ミャンマー、ブータンあたりの山岳部が原産です。 現在は「雲南省」ですが、かつて「蜀」とも呼ばれていた地域ですね。 実は烏龍茶や緑茶と同じツバキ科の常緑樹で、この葉を摘んで完全に発酵させて作ります。
中国でお茶は太古の昔から飲まれていたらしく、初の王朝である「夏王朝」(紀元前3000年頃)の 時代には「不老長寿の薬」として飲まれていたようです。
収穫量も少なかったので、一部の貴族しか飲めなかったようです。栽培が始まったのが4世紀ごろで、 紅茶ではなく緑茶として広く飲まれるようになったのは6世紀~7世紀にかけてです。 それから中国で茶葉の生産が徐々に増えていきます。
この頃はまだ紅茶は誕生していなく、低い湯温で作れる緑茶として広まりましたが、まだまだ 貴族しか飲めないお茶でした。
実はこの紅茶、緑茶やウーロン茶と同じ種類の葉で作られます。味が全く違うのは、葉っぱが 発酵している為なんですね。未発酵は緑茶、半分発酵したものが烏龍茶で、完全に発酵させた葉からは 紅茶ができます。以外ですよね。
そして16世紀半ば頃に、茶葉を完全発酵させて作った「紅茶」が誕生しました。諸説ありますが、 緑茶の味のバリエーションを広げて葉を発酵させていくうちに、紅茶ができたようです。
紅茶は中国から買い付けたオランダの商船からイギリスに渡り、イギリスで大流行しました。 イギリス貴族の間で大量に飲まれるようになったのはこの頃からです。 ポルトガルからイギリスへ嫁いだ王女キャサリンが発端ですね。
王女キャサリンが、貴重な紅茶に貴重な砂糖を入れて飲む、という当時では最高に 贅沢な習慣は、他のイギリスの貴族にとっても優雅なものだったのでしょう。
やがて紅茶の消費量はイギリスが世界一になり、植民地のインドやセイロンで紅茶用茶葉の 栽培が盛んになって、紅茶が世界中に広まります。
長くイギリスが紅茶の消費量世界一になっていましたが、最近ではトルコやアイルランドの方が 紅茶の消費量が多くなっています。世界中で愛されている飲み物なんですね。
日本の紅茶
日本にも紅茶が伝わりましたが、それはイギリスからでした。1887年頃なので、ちょうど 日本とイギリスが日英同盟を結ぶよりも15年ほど前、イギリスの文化が日本にどんどん 流れていた頃ですね。
その頃は日本に緑茶がありましたが、お湯の温度が高くても低くても楽しめる緑茶に対し、 紅茶は沸騰したお湯でないと雑味が出るため、緑茶の感覚で飲む日本人には最初は 馴染みにくかったようです。
やがて日英同盟後、紅茶のおいしいいれ方「ゴールデンルール」が広まり、日本でも紅茶の文化が浸透し、 現在では無糖でもおいしく飲める、オシャレで優雅な飲み物として親しまれています。
なお国内でも、純国産の紅茶の茶葉が栽培されています。三重や静岡などの緑茶の生産が盛んな地域ですね。 海外の茶葉とはまた違った風味を楽しめるかもしれません。